
ココをcheck法人(株式会社・合同会社)を設立した時
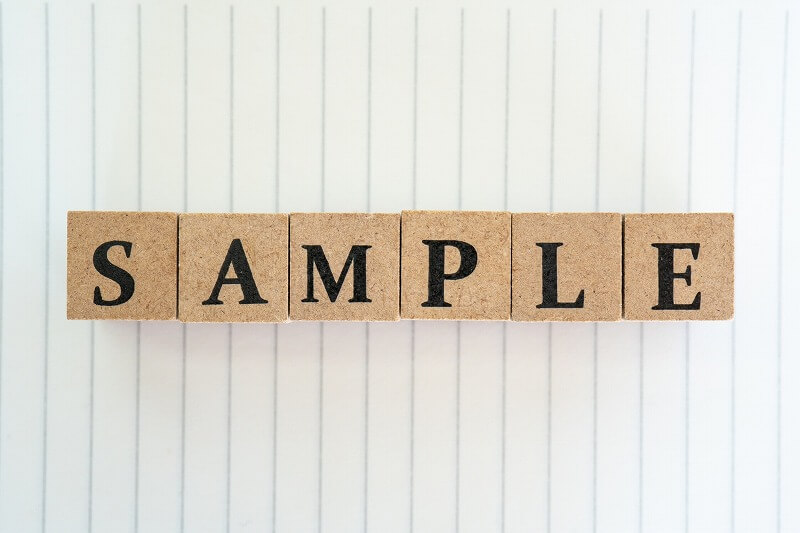
社会保険(健康保険・厚生年金)加入にともなう申請書の作成、提出を代行致します。
- 新規適用届
- 資格取得届
- 健康保険被扶養者届
|
役員以外の
従業員が |
■いない
|
健康保険、厚生年金保険の加入手続
|

|
|
|
■いる
|
健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の加入手続き
|

|
||
|
役員以外の
従業員が |
■いる
|
→
|
健康保険、厚生年金保険の加入手続
|
|
■いない
|
→
|
健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の加入手続き
|
|
役員以外の従業員が、、
- ■いない
- 健康保険、厚生年金保険の加入手続
- ■いる
- 健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の加入手続き
詳しくはこちら>>
健康保険、厚生年金の加入手続き方法
1、会社を登録する
健康保険、厚生年金保険、新規適用届を提出する。
~事前準備~
■会社(法人,商業)の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。
下記から選択
・法務局の窓口で直接手続きをする。
・郵送で手続きをする。(法務局のホームページから申請用紙をダウンロード。請求書1枚につき600円の収入印紙が必要)
・インターネットでオンライン請求をする
■登記した「本店所在地」と実際の仕事をする場所が異なる場合は、実際の仕事をする場所の賃貸契約書や公共施設の請求書の用意をする。
又はその場所で仕事をしていることが分かる書類を用意する。
■法人番号を用意する。
~事前準備~
■会社(法人,商業)の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。
下記から選択
・法務局の窓口で直接手続きをする。
・郵送で手続きをする。(法務局のホームページから申請用紙をダウンロード。請求書1枚につき600円の収入印紙が必要)
・インターネットでオンライン請求をする
■登記した「本店所在地」と実際の仕事をする場所が異なる場合は、実際の仕事をする場所の賃貸契約書や公共施設の請求書の用意をする。
又はその場所で仕事をしていることが分かる書類を用意する。
■法人番号を用意する。
|
ステップ1
|
ステップ1
日本年金事項のホームページから「健康保険・厚生年金保険、新規適用届」をダウンロードします。
|
ステップ2
|
ステップ2
必要事項を記入します。
|
ステップ3
|
ステップ3
添付資料と共に登録する住所を管轄する年金事務所に提出します。
「添付資料」
・法人,商業,登記事項証明書
・登記した住所と違う住所で登録する時はそれが分かる資料
「添付資料」
・法人,商業,登記事項証明書
・登記した住所と違う住所で登録する時はそれが分かる資料
- ステップ1
- 日本年金事項のホームページから「健康保険・厚生年金保険、新規適用届」をダウンロードします。
- ステップ2
- 必要事項を記入します。
- ステップ3
- 添付資料と共に登録する住所を管轄する年金事務所に提出します。
「添付資料」
・法人,商業,登記事項証明書
・登記した住所と違う住所で登録する時はそれが分かる資料
- Step1
- 日本年金事項のホームページから「健康保険・厚生年金保険、新規適用届」をダウンロードします。
- Step2
- 必要事項を記入します。
- Step3
- 添付資料と共に登録する住所を管轄する年金事務所に提出します。
「添付資料」
・法人,商業,登記事項証明書
・登記した住所と違う住所で登録する時はそれが分かる資料
2、人を加入させる
マイナンバー(個人番号)を準備します。
役員報酬を決めます。
役員報酬を決めます。
|
ステップ1
|
ステップ1
日本年金機構のホームページから「健康保険、構成年金保険、被保険者資格取得届/厚生年金保険者70歳以上被用者該当届」をダウンロードします。
|
ステップ2
|
ステップ2
必要事項を記入します。
|
ステップ3
|
ステップ3
会社の登録を行った年金事務所に提出。
1、会社の登録と同時にできます。
1、会社の登録と同時にできます。
- ステップ1
- 日本年金機構のホームページから「健康保険、構成年金保険、被保険者資格取得届/厚生年金保険者70歳以上被用者該当届」をダウンロードします。
- ステップ2
- 必要事項を記入します。
- ステップ3
- 会社の登録を行った年金事務所に提出。
1、会社の登録と同時にできます。
- Step1
- 日本年金機構のホームページから「健康保険、構成年金保険、被保険者資格取得届/厚生年金保険者70歳以上被用者該当届」をダウンロードします。
- Step2
- 必要事項を記入します。
- Step3
- 会社の登録を行った年金事務所に提出。
1、会社の登録と同時にできます。
3、家族・親族を扶養に入れる
~事前準備~
・扶養に入れる家族、親族のマイナンバー(個人番号)を用意する。
・扶養に入れる家族、親族の年収を確認する。
・扶養に入れる家族、親族のマイナンバー(個人番号)を用意する。
・扶養に入れる家族、親族の年収を確認する。
|
ステップ1
|
ステップ1
日本年金機構のホームページから「健康保険、被扶養者(異動)届、(国民年金第3号被保険者関係届)構成年金保険、被保険者資格取得届/厚生年金保険者70歳以上被用者該当届、」をダウンロードします。
- ステップ1
- 日本年金機構のホームページから「健康保険、被扶養者(異動)届、(国民年金第3号被保険者関係届)構成年金保険、被保険者資格取得届/厚生年金保険者70歳以上被用者該当届、」をダウンロードします。
- Step1
- 日本年金機構のホームページから「健康保険、被扶養者(異動)届、(国民年金第3号被保険者関係届)構成年金保険、被保険者資格取得届/厚生年金保険者70歳以上被用者該当届、」をダウンロードします。
4、健康保険証が手に届いたら
法人の設立までの期間、市区町村の国民健康保険に加入していた場合は、新しい健康保険証と、これまでお使いの国民健康保険の保険証を全て持って、市区町村の役場で保険料の精算をして下さい。
※国民健康保険の保険料は1年分を10回に分けて納めるため、年の途中で保険が変わると、保険料に過不足が出ます。
これを精算する必要があります。
※国民健康保険の保険料は1年分を10回に分けて納めるため、年の途中で保険が変わると、保険料に過不足が出ます。
これを精算する必要があります。
個人事業の場合
【B】個人事業の場合

原則、個人事業主は、国民健康保険及び、国民年金の被保険者となり、全国健康保険協会、及び厚生年金の被保険者にはなれません。
ただし、、、
1、(※1)理容・美容・旅館・飲食店・クリーニング店等のサービス業、農林水産業、弁護士、税理士等の士業以外の業種では、個人事業主以外の従業員は、法人の場合と同じように加入手続きが必要になります。
2、個人事業主に雇われる従業員が(※2)5名以上いる場合
ただし、、、
1、(※1)理容・美容・旅館・飲食店・クリーニング店等のサービス業、農林水産業、弁護士、税理士等の士業以外の業種では、個人事業主以外の従業員は、法人の場合と同じように加入手続きが必要になります。
2、個人事業主に雇われる従業員が(※2)5名以上いる場合
- 労働保険 保険関係成立届
- 労働保険 概算保険料申告書
- 雇用保険 適用事業所設置届
- 雇用保険 被保険者資格取得届
※1に上げた業種の個人事業の場合は従業員が何人いても法人と同じ加入手続きは不要です。
※2
4名以下、または※1の業種の従業員のうち、2分の1以上の従業員が同意する場合は法人と同じように全国健康保険協会、年金に加入する事ができます。
※2
4名以下、または※1の業種の従業員のうち、2分の1以上の従業員が同意する場合は法人と同じように全国健康保険協会、年金に加入する事ができます。
|
業種・適応人数
|
適応する保険制度
|
加入する場合
|
|
|
個人事業主
|
■理容、美容、旅館、飲食店、
クリーニング店等のサービス業、農林水産業、 弁護士、税理士等の士業以外(人数不問) |
・国民年金
・国民健康保険 |
従業員の1/2以上の同意で全国健康保険協会・厚生年金に加入できる
|
|
■4人以下
|
|||
|
■5人以下
|
・全国健康保険協会
・厚生年金保険 加入しなければならない |
||
|
手続き
|
作成書類・作業内容
|
料金
|
|
会社を立ち上げた時、社会保険に加入
|
健康保険・厚生年金保険新規適用届の作成・提出・登記簿謄本の取り寄せ等、
届け出に必要な業務 |
20,000円
|
|
従業員を雇い入れた時、労災に加入
|
労働保険関係成立届の作成・提出
概算保険料申告書の作成・申告 ・登記簿謄本の取り寄せ等、届出に必要な業務 ・概算給与額を算出と保険料の計算 |
30,000円
|
|
週20時間以上働く従業員を雇い入れた時、
雇用保険に加入 |
雇用保険適用事業所設置届
・登記簿謄本の取り寄せ等、届出に必要な業務 |
15,000円
|
|
雇用契約書の作成
|
ひな型の作成
|
15,000円
|
|
就業規則の作成
|
打ち合わせ2~3回
就業規則、36協定の作成・提出 |
20,000円
|
|
時間外労働について
|
36協定書の作成・提出
|
5,000円
|
|
その他協定書の作成
|
応相談
|
5,000円~
|
|
各種変更手続き
|
社会保険・労働保険・雇用保険の名称・住所等
変更届作成・提出 |
5,000円/1件
|
毎月の手続き

労災保険・雇用保険加入にともなう申請書の作成、提出を代行致します。
- 労働保険 保険関係成立届
- 労働保険 概算保険料申告書
- 雇用保険 適用事業所設置届
- 雇用保険 被保険者資格取得届
Q&A
社会保険の手続き
Q新規適用届の㉓番号等区分には「法人番号」と「法人番号等」のどちらを記入すれば良い?
A■登記簿謄本(正式名称登記事項照明)に記載されているのは法人番号(12ケタ)です。
これは法務局が登記された法人の管理に使います。
■法人番号は行政手続き等で法人を管理する時に使います。
こちらは国税庁のホームページで検索できます。
健康保険や厚生年金の加入手続きは「行政手続き」となるので、
新規適用届には法人番号を記入するのをおすすめします。
これは法務局が登記された法人の管理に使います。
■法人番号は行政手続き等で法人を管理する時に使います。
こちらは国税庁のホームページで検索できます。
健康保険や厚生年金の加入手続きは「行政手続き」となるので、
新規適用届には法人番号を記入するのをおすすめします。
Q役員報酬はいくらくらいにすればいい?
A会社を設立してすぐの段階では、報酬額を決めるのは難しいですよね。
設立した月からまとまった報酬を取れる場合もあれば、そうでない場合もあります。
初めから報酬を取れない場合は、法人の役員の報酬は1度金額を決めると、
変更できるのは決算月の翌月から3か月以内の期間に限られます。
設立した月からまとまった報酬を取れる場合もあれば、そうでない場合もあります。
初めから報酬を取れない場合は、法人の役員の報酬は1度金額を決めると、
変更できるのは決算月の翌月から3か月以内の期間に限られます。
Q法人を設立したけれど、当分役員報酬を取れない場合、健康保険・厚生年金の加入はどうすればいい?
Aテキストテキスト
労働保険の手続き
Qサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト
Aサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト
Qサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト
Aサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト
Qサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト
Aサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト


